第40回 日本安全保障貿易学会 研究大会終了
日本安全保障貿易学会第40回研究大会は、2025年9月27日(土)に安全保障貿易情報センター(CISTEC)にて開催された。ハイブリッド方式での開催により84名(会場47名、オンライン37名)のご参加を得て盛況であった。午前の自由論題セッションにて1件、午後のテーマセッション1、2にてそれぞれ3件の報告をいただいた。それぞれ現時点で関心の高いテーマであり、フロアからも活発な質問・意見が出された。
■自由論題セッションは1件のご報告をいただいた。
- (1) 長沢 健太氏より「米軍におけるドローン政策の変化を読み解く」として報告があった。2025年7月にピート・ヘグセス国防長官が導入を発表した米軍における小型ドローンの導入を進めるための諸政策には、小型ドローンの消耗品への分類等が含まれる。小型ドローンへの注力は今までの米軍におけるドローン政策の方向性、つまり大型無人航空機への注力、とは異なるものであるとして、この諸施策を運用政策、調達政策、技術政策の観点から読み解いた。
■テーマセッション
●第1セッションでは「米中対立の焦点: レアアース、関税問題」を取り上げた。
- (1) 峯村 健司氏より「トランプ関税と日本の選択」として、関税の持つ意味と日本が取るべき方策に焦点を当てた報告があった。トランプ関税は米国の製造業復活と外交的圧力を狙う手段となっていることが特徴である。日本は、関税交渉において経済安保を軸とした投資協議へと転換し、SPCを用いた融資保証型投資枠組みに合意した。利益配分9対1など不平等批判もあるが、他国と比べて優位な投資スキームを有効活用することで、サプライチェーン再構築など日本の国益、日本企業の収益にも結びつけていく発想が重要とした。
- (2) 土居 健市氏より「レアアースの地経学:中国の国際供給支配と輸出管理の変容」として、レアアース分野で中国が地経学的パワーを意識しながら輸出管理を強化していることについて報告があった。中国は1980年代からレアアース産業を垂直統合し、国際的な供給力を高めてきた。WTO敗訴を経て露骨な禁輸から「ルールに基づく国際秩序」を意識したパワーの行使へ転換し、輸出許可制による実質的規制強化で米国をはじめとするレアアース需要国の揺さぶりを試みている。現在はWTOルールを意識しつつISO標準規格を通じた規範支配へ拡張し、既存の国際制度を活用して上流から下流に至るまでのレアアース産業の支配力強化を目指している。日本は採掘多角化だけでなく、精製業の再強化や標準化戦略で対応すべきとした。
- (3) 藤原 智生氏より「中国のレアアース等輸出管理の強化と日本企業への影響、実務上の課題と対応」として報告があった。中国は安全保障貿易管理法制を整備し、モノ、データ、技術の越境移転の法制度を急速に作り上げてきた。特に2025年4月のレアアース7種の輸出管理強化以降、日本企業は許可取得の遅延、再輸出規制的な審査、税関検査の強化などの影響を受けている。加工度の違いによる該非判定、サプライチェーン情報提出と営業秘密の保護との関係などの課題がある中、予見性確保のために包括許可取得拡大とともに再輸出規制の動向を注視すべきとした。
●第2セッションでは「新しい時代のDual-Use -ドローン、AI、ロボット」を取り上げた。
- (1) 小木 洋人氏より「ドローン製造戦争:ウクライナ戦争におけるもう一つの戦場」として報告があった。ウクライナ戦争では低コストで大量生産可能なドローンが主戦力となり、戦況を左右している。ロシアはイラン製ドローンのライセンス生産で増産し、中国経由の電子部品やNVIDIA製の汎用エッジAIを組み込んでいるとされる。一方ウクライナは中国の規制で部品調達が困難となり、欧州諸国との共同生産を追求している。ロシア製ドローンに用いられる部品の汎用性を踏まえれば、輸出管理のみで対応することは不可能であり、西側によるエッジAI技術の厳格管理に努めつつも、同時にウクライナへの部品供給量でロシアが得られる物量を上回るという全体戦略への転換が必要とした。
- (2) 栗原 聡氏より「SFと現実の境界を越えるAIロボット」として報告があった。人間の道具として始まったAIであるが、その技術の急速な進化により人間の認知や判断を凌駕する自律型AIが現実化しつつある。生成AIや群AIの発展は安全保障分野にも直結し、もはや「使わない」選択は不可能となった。AIの軍事利用と民生利用が不可分なDual-use時代において、技術者は倫理や安全保障への責任を自覚し、制御不能な自律AI社会にどう備えるかが問われているとした。
- (3) 清岡 克𠮷氏より「Physical AIと自律兵器 - 安全保障への新たな含意」として報告があった。Physical AIとは、現実世界の物理法則を学習することで、物理的な入力を理解し自律的に知覚・推論・行動できるAIである。研究の蓄積は従前より行われてきたが、Physical AIとしてのラベリングは、2025年に提唱された。従来の情報処理AIに加え、センサーやシミュレーション環境を活用し、物理的出力を伴うタスクをこなす。UGVなど自律兵器の高度化や自然言語による指示理解により、戦場での運用効率が大幅に向上する。一方、推論や駆動に非常に多くの電力が必要となるため、バッテリーの高性能化などの電力供給が実装の課題とした。
■閉会挨拶(鈴木会長)
本日の研究大会も充実したものになり、ご参加いただいた皆様に感謝する。今回初めてCISTECの会議室を提供いただきスムーズに進行できた。ご尽力に感謝する。
安全保障貿易学会は、輸出管理と外為法を中心とする規制の問題を扱ってきた。ここは強みとして継続しつつ、関税や他国の輸出規制など安全保障と貿易に関わるところでさらにウイングを広げ、様々な枠組みで議論ができるテーマを用意していくことで、よりトータルに日本の経済、政治、安全保障に貢献していきたいと考えている。皆様のご協力をよろしくお願いしたい。
2025年10月
日本安全保障貿易学会 会長 鈴木 一人


<会場>
日本安全保障貿易学会 第40回 研究大会プログラム
日時:2025年9月27日(土)
11:15~11:50 自由論題セッション
13:00~14:50 第1セッション
15:00~16:50 第2セッション
会場: (一財)安全保障貿易情報センター(CISTEC) 5F会議室
東京都港区虎ノ門1-1-21 新虎ノ門実業会館
■自由論題セッション 11:15~11:50
(1)長沢 健太氏(拓殖大学)
「米軍におけるドローン政策の変化を読み解く」
司会討論者: 宮脇 昇氏(立命館大学(学会副会長))
■テーマセッション
●第1セッション <米中対立の焦点:レアアース、関税問題> 13:00~14:50
(1)峯村 健司氏(キヤノングローバル戦略研究所)
「トランプ関税と日本の選択」
(2)土居 健市氏(地経学研究所)
「レアアースの地経学:中国の国際供給支配と輸出管理の変容」
(3)藤原 智生氏(JETRO)
「中国のレアアース等輸出管理の強化と日本企業への影響、実務上の課題と対応」
司会討論者: 鈴木 一人氏(東京大学(学会会長))
●第2セッション <新しい時代のDual-Use -ドローン、AI、ロボット> 15:00~16:50
(1)小木 洋人氏(地経学研究所)
「ドローン製造戦争:ウクライナ戦争におけるもう一つの戦場」
(2)栗原 聡氏(慶應義塾大学)
「SFと現実の境界を越えるAIロボット」
(3)清岡 克𠮷氏(防衛研究所)
「Physical AIと自律兵器 - 安全保障への新たな含意」
司会討論者: 高野 順一氏(日本輸出管理研究所(学会副会長))
■自由論題セッション

長沢 健太氏
「米軍におけるドローン政策の変化を読み解く」

司会討論者:宮脇 昇氏
■テーマセッション
●第1セッション <米中対立の焦点:レアアース、関税問題>

峯村 健司氏 「トランプ関税と日本の選択」

土居 健市氏 「レアアースの地経学:
中国の国際供給支配と輸出管理の変容」

藤原 智生氏 「中国のレアアース等輸出管理の強化と日本企業への影響、実務上の課題と対応」

司会討論者:
鈴木 一人氏
■テーマセッション
●第2セッション <新しい時代のDual-Use -ドローン、AI、ロボット>

小木 洋人氏 「ドローン製造戦争:ウクライナ戦争におけるもう一つの戦場」
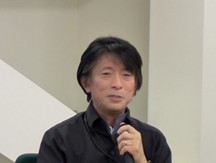
栗原 聡氏 「SFと現実の境界を越えるAIロボット」

清岡 克𠮷氏 「Physical AIと自律兵器- 安全保障への新たな含意」

司会討論者:高野 順一氏
